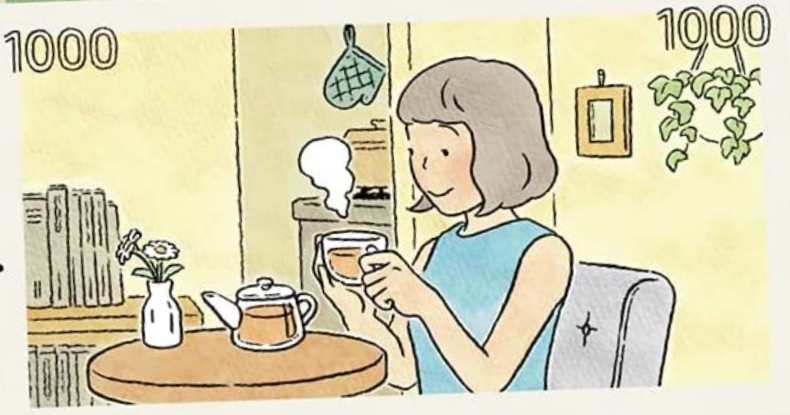娘の大学受験が終わり、あっという間に1年が経ちました。

半分くらいがオンライン授業だった昨年と比べると、今年はほぼ対面授業でスタートしています。
(今後の状況次第で変更あり)
学内の本屋さんも学食も混んでいて、今さらながら「大学ってこんなに学生がいたんだね」と驚いている娘。

楽しそうで何よりです
そこで今回は、親から見た「教育学部の大学1年生の1年間」を振り返ってみました。
この記事をおすすめしたい人
- 教育学部の学生の様子を知りたい人
- 保育学科、幼児教育学科を目指している受験生
- 受験生を持つ保護者の方
※下記の内容は、娘が通っている大学についての個人的見解です。特に履修については、学校によって内容が違いますので、詳細はそれぞれの学校でご確認ください。
幼児教育学科は圧倒的に女子が多い世界


娘が入学したのは、教育学部の幼児教育学科。
卒業生の多くが保育士や幼稚園の先生になる幼児教育学科は、圧倒的に女子が多いです。
(男子生徒は、学年にたった1人だけ。)
幼稚園から高校の先生まで、取りたい免許によっていろいろな学科がある教育学部は、学科によって、学生のカラーがだいぶ違います。
娘の観察によると、学生の分類はこんな感じ↓
※あくまでも個人的見解です。
- 男子学生が多い→理科、社会科、技術科
- 女子学生が多い→幼児教育、家庭科
- 授業コマ数が多くて大変そう→小学校理科
- 美人さんが多い→音楽科
- 荷物が多い→美術科
- 個性派→教職免許を取らない系(多文化共生など)
- Tシャツ短パン率が高い→体育科
少人数授業、ガッツリ多めの課題、長期休みの宿題?!
教育系あるある:ほぼ必修科目

大学の授業は、1年生は教養科目が多く、2年生になってから本格的な専門科目の授業が始まるところが一般的ですが…
2〜4年生で実習が入る教育系の学科は、1年生から専門の必修科目が半分以上入っています。
単位を落とすと教育実習に行けなくなってしまう場合もあるので、1年生から気が抜けません。
教育系あるある:専門以外の教職免許も取りがち

教育系の学生は、卒業要件の教職免許以外に、追加の免許を取る子が多いです。
娘が所属している「幼児教育学科」では、幼稚園教諭1種と保育士の資格が取れるのですが、学科の半分くらいの学生は、追加で「小学校教諭」の免許も取ります。
逆に「小学校教諭」を取る学科の子が「幼稚園」や「中学校・高校」を追加したり、「中学校・高校」の子が「小学校」を追加したり…。
最近は、幼稚園・保育園と小学校、小学校と中学校のギャップをなくすための交流も行われているので、両方の免許を持っていると役に立ちそうですね。
卒業後に、幼稚園ではなく小学校の先生になる人も毎年います。
その他「特別支援」「社会福祉主事」「司書」「司書教諭」「学芸員」などの資格を取る学生もいます。
就職の幅を広げるためにも、知識を深めるためにも、興味があるならとりあえず取っておいたほうがいいと思います、大変そうだけど。

もし途中で嫌になってしまったらやめればいいし、取得単位は単位数としてカウントされるので無駄にはならないし…
ただその分、コマ数の関係で、教職以外の選択科目が取れなくなることもあります。
親としては、子どもの希望どおりにやってくれれば、追加免許を取る取らないはどちらでもかまいませんが、

学費が変わらないのに、他の免許が取れるなら取っとけばいいのでは。
というセコい気持ちも、ややあります。
4年で卒業するのは無理ですが、幼稚園から高校の先生までの免許をコンプリートする学生も、たまにいるそうです。
※5年(?!)通ったり、大学院に進めば可能
オンライン授業あるある:課題が多い

昨年はオンライン授業が多く、どの授業も毎回、課題レポートの宿題が出されていました。
常に課題に追われていて、毎晩深夜まで、部屋からパソコンを叩いている音が…

塾の講師のアルバイトをしていたので、課題が重なると大変そうでした
↑結局、夜に課題レポートに取り組む時間を確保したいので塾のアルバイトは1年でやめ、2年生からは朝早くにカフェで働くことにしました。

先生との距離が近い少人数授業

教育系は学科の人数が少なく、必修科目が多いので、授業のメンバーが毎日ほぼ一緒です。
授業をサボる…なんてことは、ありえません。
ただその分、同じ学科の学生同士や教授との距離感が近くなり、分からないことはすぐ聞ける環境は、素晴らしいと思います。

大学生なのに、教授が学生の名前をみんな覚えているなんて、スゴい!
成績はネットで確認、成績が悪すぎる場合は親に連絡がくる
成績は、パソコンでポータルサイトから確認できます。
教育学部の場合、単位はもちろん大事ですが、5段階の評定も重要です。
なぜなら、平均評定が基準より低いと、教育実習に進めなくなるので。
あまりに成績が悪い場合は、大学から保護者に連絡が来るそうです。
教育実習の予約は自分の住んでいる市で

教育学部が他の学部と一番違うところは「教育実習」があるところ。
幼児教育学科では、保育園・特別支援学校・幼稚園などで2年生から教育実習や見学をするための予約を、1年生の終わり頃から始めます。
基本的には、自分の住んでいる自治体の窓口に、学生が自分で連絡を取って予約します。
※上京組の学生は、大学近くの自治体にお願いするそうです。
ただし、自治体によっては大学(担当教授)からの申込みが必要だったり、実習時期が希望どおりではなかったり、なかなか決まらない場合もあり、学生と教授との密な連携が必要になります。
長期休みが他学科とズレている?
他の学科よりも夏休みが長い教育系の学科。
なぜなら、夏休み中に教育実習をするから。
なので、教育実習がある人は夏休み中も忙しいのですが、1年生は10月まで完全に「休み」です。
そのかわり、年末年始の休みはほとんどありません。
その上、冬休みの宿題(課題)もあります!
基本黒髪、尖ったオシャレさんは少なめ、みんな真面目で良い子

実習がちょこちょこあることもあり、教育系の学生の髪は、基本的に黒髪(〜やや茶髪)。
服装も普通のカジュアル系が多く、極端に派手な子や尖ったオシャレさんはいないです。

先生になりたい子たちの集まりなので、真面目な子が多そう
娘は、他大学に行った友達のキラキラしたInstagramを見て「ウチの大学、地味すぎて…ヤバい」と焦っています。

まあ、高校生のときの服装で通えるのでエコかもしれません
ちなみに、現役で入学した女子は、約2年後の成人式に向けて髪を伸ばしている子が多いので、みんな似たようなロングヘアになりがち。
アルバイトは、塾や学童保育が多め?

幼児教育学科の1年生を見渡すと、学童保育や保育園、塾などの先生系アルバイトをしている子が3分の1くらい。
あとはみんな、カフェや居酒屋などの飲食店で働いているそうです。
予想していたより先生系アルバイトが少ないのは、多分、学校が忙しすぎて、シフト調整ができるバイトでないと無理だからかと。
また、実習期間は1ヶ月くらいアルバイトできないので、夏休みなどに集中して短期バイトで働く学生もいるようです。
彼氏彼女とは、どこで出会う?

オンライン授業が多くて、サークル活動もなかなかできなかった昨年度。
彼氏や彼女がいる人は、どうやって出会っているのか…謎でした。
娘に聞いてみたところ、まず周りで彼氏彼女がいる人が、3人にひとりくらい。
つまり、いない人のほうが多い。
出会いは、だいたい下記の3パターン。
- アルバイト先で知り合った
- 高校生のころから付き合っていた
- 学内で知り合った
3の「学内で知り合った」人の中には、選択科目のオンライン授業で、グループで話し合いをするためのチーム分けで出会い(=つまり、パソコンの画面の中!!)、好感を持ったためInstagramを探してフォローし、仲良くなった人もいるとか。
現代の若者の恋愛は、こんな感じ…らしいです。
まとめ
親目線で、今どきの大学生を観察して思うことは、
みんな真面目に勉強していてエライ!
本当にそう思います。
我々が若かった頃は、大学生なんてほとんど勉強していなかったような…
(もちろん、ちゃんと勉強していた人もいると思いますが。)
コロナの感染対策で、不自由な学生生活ですが、みんな頑張っているなぁ…と感心します。
残りの3年間も、大学生活を楽しんで、いろいろな経験をしてほしいと思います。